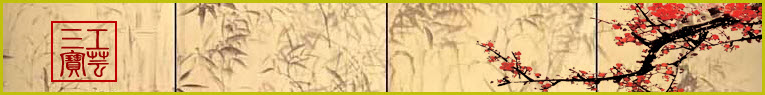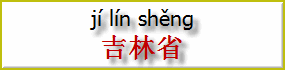

吉林省(きつりんしょう・チーリンショウ) 中国東北地区の中部にある省。西は内モンゴル自治区、東はロシア連邦、南東は朝鮮民主主義人民共和国と接する。省域は東部のチャンパイ山脈(長白山脈)につらなる山地と、西部のトンペイ平原(東北平原)の平野からなる。漢族のほか、朝鮮族、満族など35の少数民族がすむ。面積は18万7000km2。人口は2699万人(2002年)。省都はチャンチュン(長春)である。 |
| ■経済 |
平野部ではトウモロコシ、大豆などが、延辺朝鮮族自治州などでは水稲が栽培されている。東部は長白山脈を中心に林業が盛んである。西部のパイチョン(白城)周辺ではヒツジの放牧がおこなわれている。中国の重要な食糧生産、林業の基地のひとつである。チョウセンニンジン、鹿茸(ろくじょう:シカの袋角)、テンの毛皮は「東北三宝」といわれる特産品である。長春を中心とする自動車製造、チーリン(吉林)市を中心とする石油化学、食品、鉄鋼、紙・パルプ、医薬品などの工業が発達する。自動車、鉄道車両、鉄合金は国内1位の生産量をほこる。長春の絨毯(じゅうたん)、吉林市のガラス細工などの工芸品も有名である。 ペキン(北京)~ハルピン(哈爾浜)鉄道を中心とする鉄道網が発達する。また省内をながれる第二ソンホワチアン(松花江)は内陸水運の動脈である。長春などには空港がある。 |
| ■歴史 |
かつては満族とモンゴル族の遊牧と狩猟の地だった。明代末以降、満族の南下、清王朝の成立にともない、祖宗の地に漢民族を流入させないよう封禁政策がとられ、農地は荒廃した。1882年以降、華北地区からの移民が急増し、1900年前後には各地に府県がおかれるようになった。31年の満州事変以降、日本の傀儡(かいらい)政権「満州国」がつくられ、首都は長春におかれた。日本資本による鉱物採掘、森林の伐採がすすめられ、20以上の県で日本の農民による開拓がおこなわれた。54年に行政範囲の再編をへて今日の吉林省が設置された。 1992年以降、対外経済交流が加速された。94年末までに省内の外資直接投資額は2億4192万ドルに達し、三資(合弁、合作、全額外資)企業は2887社にのぼった。とくに海への出口確保という悲願達成のため、ロシア連邦、朝鮮民主主義人民共和国との国境地帯である図們江(豆満江)地域総合開発プロジェクトに意欲をみせている。宮城県、カナダのサスカチュワン州などと友好関係をむすんでいる。 |
| ■観光と文化 |
北朝鮮との国境をなす長白山脈は原始林におおわれ、自然保護区としての指定をうけており、山頂には火山湖の天池がある。松花江の上流にある豊満ダム周辺は観光地化され、国内最大のスキー場がある。そのほかに高句麗文化遺跡(注1)や渤海遺跡(注2)などの史跡がある。また、43の大学や光学精密機械研究所など172の国公立研究所があり、中国有数の学術研究の中心地である。吉林大学の日本語教育は国内では有名である。長春映画製作所は中国の代表的な撮影所として知られる。 |
| (注1)高句麗(こうくり) | (注2)渤海国(ぼっかいこく) |
前1世紀後半から後668年まで存続した朝鮮の古代国家で、中国東北地方の中南部一帯から朝鮮半島の中部にかけて支配した。高麗、句麗、狛、貊(はく)などと書く場合もある。半農半猟の生活をおくっていた貊族は、中国の前漢王朝の力が弱まった前1世紀後半、鴨緑江の支流にあたる佟佳江(とうかこう)流域の桓仁(かんじん)を中心に小国連合をきずいた。高句麗人とはこの貊族の一部と考えられている。 204年に都を国内城(現、中国吉林省集安市)にうつして遼東方面をめぐって公孫氏や華北の諸王朝と攻防をくりかえした。また、中国が五胡十六国時代をむかえた4世紀前半には、戦乱にやぶれた多くの漢人が高句麗に亡命し、高句麗の政治や文化、外交などに影響をあたえた。355年には五胡十六国のひとつ前燕(ぜんえん)が故国原王を冊封(さくほう)、高句麗は朝鮮諸国のうちでは最初の中国王朝の内臣となった。 4世紀後半からは広開土王が遼東地方に領域を広げ、それにつづく長寿王の代には朝鮮半島にも広大な領土を獲得した。長寿王の427年には、平壌へ都をうつし、朝鮮半島における三国の対立が激化する中で領土は拡大をつづけた。しかし6世紀半ばになると、南から新羅の巻き返しにあい、さらに西方からは数度にわたる隋軍の侵攻をうけることになった。高句麗はこれらの侵略をすべてしりぞけたが、ついに668年、隋にかわった唐と新羅の連合軍にほろぼされた。 595年に高句麗から渡来して聖徳太子に仏教をさずけた僧の慧慈(えじ)に代表されるように、高句麗と当時の日本との間には文化的な交流が盛んにおこなわれていた。高松塚古墳の壁画にも、高句麗の壁画古墳の影響がみられる。 ▲遺跡 高句麗は当初、都を鴨緑江沿いの集安においたため、現在でもこの周辺には広開土王碑をはじめ、数多くの古墳群がのこっている。古墳は積石塚とよばれる、川原石をつみあげたものである。この中には松岩里古墳群のように平面型が前方後円型をしめすものがあり、日本の前方後円墳の源流とする学者もいる。 その後、都を現在の平壌付近にうつしたため、ここにも安鶴宮跡、長安城跡など多数の遺構がのこっている。徳興里古墳では5世紀代の彩色壁画が発見され、その構図などが、上にのべたように日本の高松塚古墳と近似している点で注目された。また、積石の積み方などが日本の弥生時代後期に出現する四隅突出墳丘墓によく似ていることも近年注目されている。 |
668年に唐・新羅連合軍によって高句麗がほろぼされたあと、698年に高句麗の遺民と靺鞨(まっかつ)人によってつくられた国家。中国東北部から朝鮮半島北部を領土とし、はじめ震国と称した。始祖は大祚栄。半島中南部を統一した新羅と併存したこの時期を、朝鮮史では南北国時代ともいう。 このころ唐は、突厥をはじめとする周辺諸国の活動になやまされていたため、713年に大祚栄を渤海郡王としてその存在を容認、以後渤海が国号となった。官制は唐にならい、文化面においても、高句麗的要素をのこしつつも唐の影響が大きい。9世紀前半には、唐から「海東の盛国」といわれるほどさかえたが、10世紀にはいって支配層に内紛が生じ、926年、契丹の侵略をうけて滅亡した。滅亡の前後には多数の渤海人が高麗に亡命している。 日本と渤海国は、はじめ新羅を牽制する必要から交流をはじめたが、やがて貿易が拡大し、文化的な交流も活発になった。日本にとって渤海国は、唐への中継地として重要な位置を占めていた。 ・・・・・・・・・・・・ 渤海使(ぼっかいし) 古代、渤海国から日本に派遣された外交使節。使節は727年(神亀4)~919年(延喜19)に34回におよび、能登や伯耆(ほうき)、出雲など日本海の港へ来着した。一方、日本からの遣渤海使は13回あった。 渤海国は、高句麗がほろんだのち、旧高句麗領を中心として成立した国で、唐の冊封をうけ、北西の突厥、南の新羅にはさまれて、きびしい国際情勢のもとにあった。そのため、初めは、日本とむすんで新羅を牽制(けんせい)する、という政治的な目的で渤海使が来航し、遣渤海使は日本側が渤海の使節をおくる使を派遣するというケースが多かった。遣渤海使13回のうち10回はそうした送使である。 8世紀後半からは東アジアの国際情勢が安定し、811年(弘仁2)の送使を最後に、日本からの遣渤海使はおわったが、その後も交易を目的とする渤海使が、国の滅亡(926)直前まで来航した。8世紀末以降に来航した使節は、毎回100名余の人員からなり、熊や虎などの毛皮、蜂蜜、人参、暦(宣明暦)、仏典などをもたらし、日本側の交易品はおもに絹や糸などの繊維製品であった。 |
(資料出所:マイクロソフトエンカルタ2007)
≫≫≫ ≪≪≪