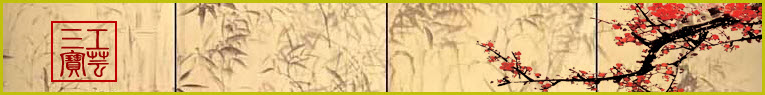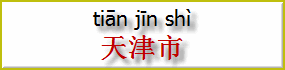

天津(てんしん・ティエンチン) 中国の華北平原北部にある中央政府の直轄市。中国第2の工業都市で、北はイエンシャン山脈(燕山山脈)、東はポー海(渤海)にのぞみ、ハイホー(海河)の下流域にある。国内の南北交通の分岐点にあたる要所で、100km北西に位置するペキン(北京)とは高速道路でむすばれている。面積は1万1920km2(市区は7418km2)。人口は914万人(市区は748万人。2001年)。 |
| ■経済 |
国内で近代工業がもっともはやく発達した都市のひとつで、工作機械、自動車、エレクトロニクス、化学、鉄鋼、紡績などの工業が盛んな総合工業都市である。6500余の工場が、海河沿いにたち、伝統工業では絨毯(じゅうたん)が有名。国内の大都市の中では石油、天然ガス、塩、地熱などの資源にめぐまれているのが特徴である。南部の大港油田、中国初の海上油田である渤海油田からは年間470万tの石油、4万m3の天然ガスが産出し、国内最大のチャンルー(長廬)塩田からは年間200万t以上の塩が生産される。周辺農村は小麦、綿、果樹などの栽培が盛んで、特産の小站米(日本種)や天津甘栗は国内外に知られている。海岸地域ではクルマエビなどの養殖がおこなわれている。 150km以上の海岸線をもつ天津は、華北第1の貿易港としてさかえる。9000mの岸壁、55基の1万トン級バース(船舶用停泊施設)がある港は、年間1億2906万tの貨物をさばき(2002年)、160カ国以上と貿易をおこなっている。北京への海上からの玄関口であると同時に、中国北部の物資集散地として商業が発達し、シャンハイ(上海)、コワンチョウ(広州)とともに全国的規模の商都である。 |
| ■歴史 |
元代以来、大運河にそう南北水運の要衝としてさかえ、明代には「天子の津(渡し場)」と称された。アロー戦争後の1858年、この地で天津条約がむすばれた。さらに60年の北京条約によって国際貿易港として開港し、イギリス、日本など9カ国の租界がもうけられた。以来、外国資本が経営する紡績などの工場ができ、多くの外国商社も進出した。 1958~66年にホーペイ省(河北省)の省都となった以外は、長い間、中央政府の直轄下におかれていた。80年代に沿海開放都市に指定され、84年に経済特区並みの優遇政策がうけられる経済技術開発区がもうけられた。しかし大きく発展をとげたのは90年代になってからで、電子、食品加工、機械などの外資系大企業が進出した。天津港保税区には約3000社が入っている。神戸市、四日市市、千葉市と友好関係をむすんでいる。 |
| ■観光と文化 |
| 市内には周恩来記念館、望海楼、天後宮などがあり、郊外には1000年前にたてられた独楽寺、海河河口南岸タークー(大沽)の砲台跡などの旧跡がある。明・清時代の古い町並みを再現した長さ600mの古文化街や、天津名物の肉饅頭(天津包子:パオズ)で有名な老舗「狗不理(ゴウブーリー)」など100軒余りの食堂がならぶ南市食品街も観光名所となっている。名門の南開大学(1904年創立)、天津大学をはじめ、28の大学、300余の科学研究機関がある文化の中心地である。 |
(資料出所:マイクロソフトエンカルタ2007)
≫≫≫ ≪≪≪
地域写真募集中 |
| 地域風景での掲載写真はすべて本サイト閲覧の皆様から提供していただいたものでございます。
お気に入りの地域写真を下記アドレスまで送って頂ければ、選考の上で掲載いたします。 サイズはなるべく350×200以上、出所と簡単な紹介を付けていただければけっこうです。 |